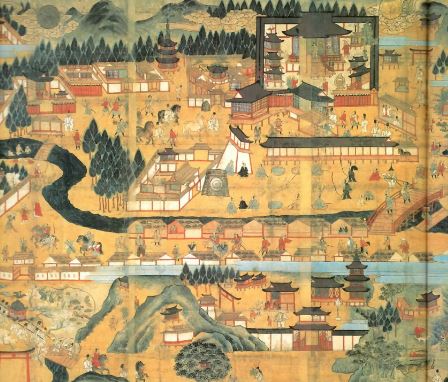秋の七草の風習を探ってみる

秋の七草は食用というよりは観賞用として考えられた七草です。
旧暦の7月、8月、9月が秋ですので、「秋の七草」の鑑賞時期はこの頃で、現在の暦にあてはめると、9月中旬ごろから11月初旬ごろになります。
秋の七草に挙げられる植物の中には、薬草として用いられてきたものがほとんどです。
秋の七草の顔ぶれは、奈良時代の貴族・歌人である山上憶良が詠んだ、万葉集の2首の歌が由来です。
秋の七草を覚えるにはぴったりな歌ですね。
1首
秋の野に 咲きたる花を 指折り(およびをり) かき数ふれば 七種(ななくさ)の花
2首目
萩(はぎ))の花、尾花(おばな)、葛花(クズ)瞿麦(クバク:なでしこ)の花、姫部志(をみなへし) また藤袴 朝貌の花
「朝貌の花」の指すのは、朝顔、木槿(むくげ)、桔梗、昼顔など諸説ありますが、(キキョウ)とする説が最有力です。
秋の七草は春の七草のように直接何かをするという行事はありませんが、古来より花野(秋の野の花が咲き乱れる野原を「花野」という)を散策して短歌や俳句を詠むことが行われていました。
春の七草にあるような「秋の七草粥」というものもありません。
食べられないわけではないようですが、食用としてあるわけでないです。
どちらかというと薬草としての役目が大きいです。
七草の意味を踏まえて具体的に紐解きましょう
●萩(はぎ)
葉を落として冬を越し、春には再び芽を出します。
根が、咳止めや胃の痛み、下痢止めなどに効果があります。
「草かんむり」に「秋」と書く、まさに秋を代表する花の1つです。
秋のお彼岸にお供えする「おはぎ」の名の由来にもなっています。
〈花言葉〉・・・思案、内気、想い、前向きな恋、柔軟な精神
●薄(すすき・尾花のこと)
「すくすくと立つ木」という意味があります。
根や茎に、利尿作用があります。
すすきの穂が動物の尾に似ていることが、名前の由来と言われています。
お月見にはかかせない飾りの1つです。
〈花言葉〉・・・勢力、生命力、活力、隠退、悔いなき青春、心が通じる
●葛(くず)
上品な和菓子であるくず粉の原料になり、根は現代でも風邪薬で有名な葛根湯に用いられています。
肩こりや神経痛にも効果があります。
葛湯、葛切り、葛餅など今でも親しみ深い植物の1つです。
葛の根を乾燥させた「葛根(かっこん)」は民間治療薬として、風邪や胃腸不良などの際に用いられます。
〈花言葉〉・・・治療、活力、根気、努力、芯の強さ、恋のため息
●撫子(なでしこ)
「撫でたいほど可愛い子」に例えられる花です。
煎じて飲むと、むくみや高血圧に効果があります。
日本女性の清楚さを表現した「大和撫子」の「撫子」は、この花のことです。
可憐な淡紅色の花を咲かせます。
「枕草子」の中で、清少納言は撫子の美しさは草花の中で第1級品であるとしています。
〈花言葉〉・・・純愛、無邪気、思慕、貞節、才能、大胆、いつも愛して
●女郎花(おみなえし)
「花の姿が女性を圧倒するほど美しい」と言われている花です。
根と全草には解毒・鎮痛・利尿などの作用があります。
女郎花の名前の由来は、花の美しさが美女を圧倒するためという説があるほど、優雅で美しい花として古代の人に親しまれた花です。
そのため、多くの歌や句にも詠まれています。
〈花言葉〉・・・美人、親切、はかない恋、心づくし、約束を守る
●藤袴(ふじばかま)
花の形が袴を連想させることからこの名前がついたそうです。
乾燥させたものを煎じて飲むと、糖尿病に効果があります。
藤袴は、花の色が淡紫色で、弁の形が筒状で袴に似ていることからこの名前が付けられました。
乾燥させると桜餅の桜葉と同じ良い香りがするため、洗髪や香水にも用いられます。
現在では絶命危惧種に指定されており、野生の藤袴を見ることはほとんどできません。
〈花言葉〉・・・遅延、躊躇、思いやり、あの日を思い出す、優しい思い出
●桔梗(ききょう・朝貌のこと)
五角形で青紫色の美しい花を咲かせます。
根を煎じて飲むと痰や咳、のどの痛みに効果があります。
桔梗は、その形の良さから多くの武将の家紋に用いられました。中でも明智光秀の水色桔梗の家紋は有名です。
藤袴と同様、絶滅危惧種に指定されている花です。
〈花言葉〉・・・清楚、気品、誠実、従順、変わらぬ愛、優しい温かさ
秋の七草の楽しみ方
「秋の七草」はあまりメジャーではありませんが、ご家庭や仲間内で覚えて楽しんでみてはいかがでしょうか?
面白い覚え方があるので、ご紹介します。
★「ハスキーなお袋」での覚え方★
「ハ」・・・萩(はぎ)
「ス」・・・薄(すすき)
「キ」・・・桔梗(ききょう)
「-」
「な」・・・撫子(なでしこ)
「お」・・・女郎花(おみなえし)
「ふ」・・・藤袴(ふじばかま)
「く」・・・葛(くず)
「ろ」
★「お好きな服は?」での覚え方★
「お」・・・女郎花(おみなえし)
「す」・・・薄(すすき)
「き」・・・桔梗(ききょう)
「な」・・・撫子(なでしこ)
「ふ」・・・藤袴(ふじばかま)
「く」・・・葛(くず)
「は」・・・萩(はぎ)
他にも覚えやすい語呂合わせがないか考えてみるのも良いでしょう。
まとめ
日本古来からの、秋の七草をもとに季節感を楽しむのも、忙しくしている日常から1歩離れた楽しい時間になるかもしれませんね。
日本人ならではの楽しみに浸ってみてはいかがでしょうか?