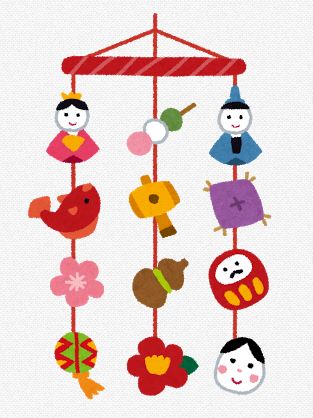節分にお化けってどういうこと?
時期こそ違うけど、仮装といえばハロウィンと言われるくらい一般的になってきました。
でも、昔は、日本にもともと節分お化けという仮装する風習があったのをご存知でしょうか?
お化けというからには、洋風にゾンビをイメージするけど、東洋なら妖怪ですよね。
実際は、どうなんでしょうか?
節分お化けとは?
節分お化けは、立春前夜の2月3日の節分の夜にの厄払いとして行われる日本古来の儀式なんですね。

この日は旧暦では大晦日、翌日の立春は元旦にあたり、新年になると恵方が変わります。
恵方参りする人間を狙う鬼や化け物から逃れるため、大晦日に普段とは異なる姿に仮装し、人間が鬼や化け物を化かし追い払う風習です。
いつもとは、まったく違う格好で、神社参拝を行う儀式なんです。
お年寄りの女性が、少女の桃割の髪型にしたり、逆に成人前の少女が大人の女性の髪型である島田に髪を結ったりします。
これは、「お化け」が「お化髪」とする語源から来ています。
そして、異装の格好、すなわち、お化けの格好のまま、神社へ新年の平穏を祈り、参拝します。
「節分お化け」は、京都や大阪の花町を中心として江戸時代末期から昭和初期にかけて盛んに行われていました。
ほんとかな?!と思うような行事ですよね。
お化けの格好をして、神社にお参りなんて、失礼にならないかと疑問に思いますよね。
今となっては、一般の行事としては無くなって、京都の祇園などの花町や東京銀座、大阪、名古屋など、一部の繁華街にその風習は残りました。
ほとんど、「節分お化け」自体を知らない人が多くなっています。
節分お化けの仮装
節分お化けの仮装は、やはり、発祥である京都の影響が強くホステスさんが芸者さんや花魁、男性スタッフは黒服を着て、太鼓持ちに仮装することが多くなっています。
発祥地の京都では、芸者や花魁では、節分お化けとしての仮装にならないので、仮装イメージを強める為に、鬼や妖怪、武将、僧侶などが多いです。
仮装といっても、かなり本格的で、衣装をレンタルしたり、髪を結うかカツラを被ったり、歌舞伎役者さながらの白塗りで、花魁道中さながら繁華街を練り歩きます。
仮装お化けをしながら、いろんなお店に挨拶周りをして、お客様からご祝儀を頂いたりします。
また、今では、「オナベ」や「オカマ」に違和感を持たない時代になったせいか、異性装が多くなりました。
その日だけ「オナベ」や「オカマ」になってしまうわけです。
この時とばかりに、自分の本当の姿?!を見せているのかもしれません。
いまでは、ハロウィンをしっかり楽しむイベントも大々的に行うので、ハロウィンの影響も多少なりとも受けることで、パーティー感覚の軽い仮装から、節分お化けに慣れ親しんだかたは、節分お化けで気合の入った本格的和風の仮装する感じがします。
節分お化けに仮装したまま神社参拝
節分おばけで仮装したまま営業が終わったら、そのままの格好でその年の恵方の神社に参拝します。
節分お化けで神社に参拝することがメインではなく、最後の締めに神社に参拝します。
でも、節分お化けの異装のままの節分の参拝することこそが、本来の節分お化けの意味なのです。
ここで、節分本来の厄払いや、ホステスさんが芸者さんや花魁などの商売繁盛を願ってお参りするのです。
節分お化けの一行が、2月3日の節分に嵐電に乗車します。
今でも、京都の花街では残っていますが、かつては町中で行われていました。
この風習を復活させるため、18年以上前から、花街・島原の司太夫が代表の島原応援団の「こったいの会」がお化けに仮装し節分参りを続けています。
毎年、一行は、最寄の四条大宮駅、すなわち壬生寺から、最寄の嵐山駅の天龍寺への移動に嵐電を利用します。
偶然にも、ご同乗出来ると、ラッキーなお客様には「節分お化け」の風習を目の当たりにして、とても楽しい経験をすることが出来ます。
このように節分お化けを行うのは、違う年齢や違う性など「普段と違う姿」をすることによって、節分の夜に、夜な夜な歩き回るとされる鬼をやり過ごすためなんです。
また旧暦では年の変わり目である1月の始まりも、大体この時期なので、方位をつかさどる神が居場所を変えたるするので、世界の秩序が大きく改組される不安定な時期と信じらていました。
節分の時期は、現世と異世界を隔てる秩序も変化して、年神様のような福をもたらす神様がやってくるのと同時に、危害をもたらす鬼もやってくるとされていたんですね。
そこで豆まきが行われているのと同時に節分お化けも儀式のひとつなんですね。
「よしわら節分お化け」が吉原で行われる?!
芸妓などが時代劇やスポーツ選手、海外の民俗舞踊など、通常の衣装とは違う様々な扮装をして座敷に出てきます。
またお客も様々な扮装をする場合もあり、お客の男性が芸妓や舞妓の扮装をして他の客の座敷に出ることもありまする。
立場を逆転してみるといったところでしょうか?!
座敷では客が他の客の座敷を覗くことは禁止されているけれども、節分お化けの時には、年に一度の例外として上がり込む事を許されています。
かなりの盛り上がりを見せます!!
節分お化けのまとめ
節分に仮装して神社に行くことは、気持ち的に失礼と感じるものの、仮装することで、鬼をやり過ごす意味もあり、なんとか厄払いをすませようとする心意気を感じます。
なかなか、地方に住んでいると節分お化けを目の当たりにすることはありませんが、ハロウィンのように気になる風習ですね!!