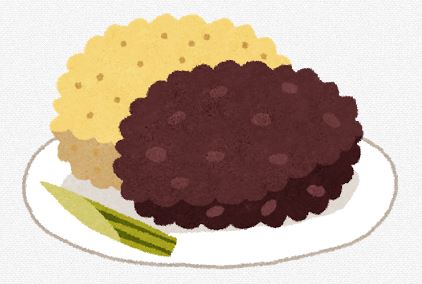鯉のぼりの起源は?
古来中国の行事が日本に伝わったのが始まり。
日本に伝わった後、日本の中で変化をしていって、日本独自の風習として根付いたのが、端午の節句すなわち、「こどもの日」です。
でも、端午の節句が、五節句の1つとされ定着したのは江戸時代のことなんです。
当時の庭に立てられていたのは、「鯉のぼり」ではなく「武者のぼり」と言われる物でした。
武者のぼりとは?
武者のぼりの起源は、戦国武将の「旗指物」にあるとされています。

例えば、時代劇の戦いのシーンで、家紋のついた旗を掲げていたり、馬に乗った武将が鎧に旗を挿して走っている。
そんな場面を見かけることがあると思います。
そこで使われている旗が「旗指物」といわれるものなんですね。
戦場で使われていたものが、庶民の間に浸透したというのは、奇妙な感じですね。
となると、武者のぼりの関係をまとめていきますよ。
武者のぼりを端午の節句に立てたワケは何!?
室町時代末期の武家社会では、「端午の節句に、旗指物を虫干しをかねて飾る」という習慣があったんです。
端午の節句の「武者のぼり」を庶民が真似た事で庶民に浸透していきました。
この習慣がやがて、日本全国各地で行われるようになりました。
とすると、気になるのは、「旗指物」と「武者のぼり」の違いです。
「旗指物」と「武者のぼり」の違いは何!?
時代劇の中で、よく目にするのは、旗指物は、家紋だけが描かれています。
庶民が立てた「武者のぼり」には、中国に伝わる道教系の神のしょうき(鐘馗)や金太郎、武者絵などが描かれていたんですね。
庶民の願いと同じように、描かれている絵には、「子供に幸せな人生を送って欲しい」、という願いが込められていたそうです。
そして、「武者のぼり」は、「絵のぼり」「節句幟(のぼり)」、が、正しい呼びかたです。
その図柄に武者絵が多いことから、一般的には、「武者のぼり」と呼ばれています。
「武者のぼり」=「武家のもの」と思われがちですが、決してそうではありませんので、勘違いをされませんようにね。
いつになると鯉のぼりが誕生するのでしょうか?
鯉のぼりの誕生はいつ!?
鯉のぼりのベースが出来たのは、江戸時代の中期頃です。
江戸時代の中期以前より、立身出世のシンボルとして、「武者のぼり」には「鯉の滝登り」の図柄が描かれていたんです。
「鯉の滝登り」の図柄から作られた「鯉の小旗(まねき)」が鯉のぼりの基本となりました。
小旗とは、幟旗の付属品のことを指します。
それ以降、小旗は、時代と共に変化、独立して、現在の「鯉のぼり」となりました。
当初は立体的な形状になっていなくて、「立体型の鯉のぼり」は明治時代以降のことです。
鯉のぼりの発祥の地はどこ?!
毎年、四万十川中流の高知県高岡郡四万十町十川では、4月下旬から5月上旬にかけて500匹のこいのぼりの川渡しが行われており、その発祥地として知られています。
群馬県館林市では、昭和49年から始まった世界一こいのぼりの里まつりが3月下旬から5月中旬まで開催されています。
5,000匹以上のこいのぼりが鶴生田川、茂林寺川、近藤沼、つつじが岡パークインの4箇所で掲揚されています。
高知県高岡郡四万十町十川で目の当たりすれば圧巻というか、感動するでしょう!!
実際にこの目で見たいものですね。
鯉のぼりの起源まとめ
鯉のぼりは武士の出陣に関係する道具がベースになったようですが。
今も、昔もこどもの未来を考えて立派に成長してほしい想いは変わらないようですね。