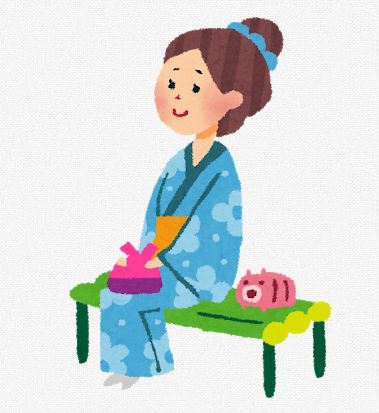浴衣の始まりはいつ?!
暑い時期になると何気なく着るようになる浴衣。
洋服と違って取り扱いに手間取ることもありますが、折角、浴衣を着る文化があるので、上手に利用してみるのがいいですね。
男っぷりを上げるのもよし、女性らしさをだすのもよろし。
そこで、浴衣の始まりを知って、浴衣良さを掴みましょう!!
浴衣の始まりは?!
浴衣の起源は平安時代までさかのぼります。

浴衣の起源は、平安時代の「湯帷子」です。
「湯帷子」の読みは、「ゆかたびら」です。
「帷子」とは麻の着物のことを指します。
当時の貴族は、蒸し風呂という方法、現代で言うところのサウナのようなものに入浴していました。
そのときに、水蒸気で、「やけど」をしないために汗を取ることが必要なこと。
また、1人だけ蒸し風呂にいるわけではなく、複数の人がいることから、自分の裸を隠す必要があることから、「湯帷子」を着用していたんですね。
湯上がり着として浴衣を着ていた?!
安土桃山時代には、風通しがよくて、また汗をよく吸い取るという浴衣の特性を生かして、湯上がりに着るようになっていきました。
このことから、浴衣は手ぬぐいならぬ「身ぬぐい」と呼ばれることもあったんですね。おもしろい!!
庶民に広がるのは江戸時代に入ってから!?
浴衣が庶民の間で着用するようになったのは江戸時代のことです。
平穏な時代になって、町民文化が発達したこともあります。
特に、江戸時代の後期、銭湯の数が増えていき、庶民もお風呂に手軽に入るようになったことも1つの要因です。
なので、湯上がり着として、浴衣が庶民へと広がっていきました。
これが湯上がり着の範囲を超え、ちょっとした外出着へと変化し、さらには、盆踊りや花見へ、揃いの浴衣を着て出かける文化が流行するまでになっていきました。
この習慣がお祭りなどで着る現代の習慣につながっていますね。
江戸時代の浴衣は大人気になり、本藍染めという技法が生まれるほど専門技術が作られていきました。
その結果、細かい模様を染めることができるようになっていきました。
専門技術の「本藍染め」という技法が生まれたことで、浴衣が優雅で美しい柄ものとなって、多くの人が楽しんで着るようになります。
夏の普段着としての浴衣へ変化?!
明治時代には、浴衣が夏の普段着としての地位を確立します。
浴衣は手ごろなんだけど、粋なものとして認められた証でもありますね。
でも、さらに浴衣が手ごろになっていったのは、明治時代に、それまでの「本藍の手染め」にかわって、「注染」という大量生産が可能な染色方法が発明されたことがポイントです。
浴衣にこだわりを見せた結果がさらに染め技術の進化になったところですね。
浴衣は、江戸時代後期から明治時代に一番着られていたようです。
浴衣に代わる洋服が広がった?!
第二次世界大戦後、産業の発展に伴い、一気に生活スタイルが洋式化します。
それは、衣服に関しても様式化が進み、和服に代わって洋服文化が広がっていきます。
この流れが、浴衣を衰退させることになっていきました。
その流れの通り、現代では、普段着として浴衣を着る人はあまりいないようです。
でも、お祭りや花火大会のときに、あえて自分なりに楽しんで、浴衣を着こなす若者が増えています。
若者にとっては、浴衣が粋なファッションとして捉えられていますね。
おすすめ浴衣って何?!
浴衣の柄を見て、あなたなりにピンと来るものがあるかもしれません。
ヒントになればいいなと思い、少しまとめてみます。
浴衣の「古典柄」が人気なのをご存知でしょうか?!
浴衣「古典柄」の意味とおすすめの浴衣
麻の葉の意味
麻は成長が早く、丈夫なので、「めでたい植物」と言われています。
麻の葉文様は男女ともに使用され、一般的には連続させて麻の葉繋ぎとして用いられることが多い文様です。
古くは平安時代の仏像の衣にも用いられるほど歴史があり、シンプルでありながら上品さが際立つ文様の一つです。
産着にも使用され、女児には赤が良いとされています。
麻の葉柄のおすすめ浴衣
臙脂色(えんじいろ)に麻の葉繋ぎ文様が映える高級仕立て上りの浴衣です。
濃い紅色が鮮やかで、目を引く意匠になっています。
二色のシンプルな生地でありながら、浴衣を覆う麻の葉繋ぎ文様が印象的な浴衣です。
牡丹の意味
牡丹の花言葉は「富貴」「壮麗」と言った気品あふれるものです。
葉の上に座っているかのように咲く牡丹は、女性の美しさを形容する「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」でもおなじみです。
大輪で咲くことから、原産地の中国では花王とも呼ばれる重厚な荘厳なイメージです。
牡丹柄浴衣のおすすめ
白の生地に緑を基調とした牡丹柄が印象的な浴衣です。
濃い暖色系の色味になりがちな牡丹をあえてさわやかなグリーンやブルーにしたことで、涼やかなイメージに仕上がっています。
帯は同系色の緑に差し色の紫で上品に引き締められています。
菊の意味
菊は皇室の正式紋として受け継がれており、「十六花弁菊紋」は日本の紋章として使用されています。
花言葉も「高貴」「清浄」など、清らかで上品なイメージです。
菊の花は高潔なイメージだけでなく、長寿の意味合いもあるので、大人の落ち着いた雰囲気に相応しい意匠であると言えます。
菊柄浴衣のおすすめ
深い紺地に、薄いブルーの菊文様が印象的な浴衣です。
菊に絡む唐草文様が、単調になりがちな菊花に動きを付け、華やかに見せています。
帯は白ですっきりとまとめられています。
朝顔の意味
朝顔の花言葉には「固い絆」「愛情」などがあります。
また、朝に咲き、昼にしぼむ様から、名の由来が「朝の美人の顔」の意味であるともされています。
支柱にしっかり絡む蔓からも、花の儚さに対し、絆の強さを感じられる花です。
朝顔柄浴衣のおすすめ
シャープな縦縞に青を基調とした朝顔が目を引く浴衣です。薄緑、紺、淡い黄色の縦縞文様に絡むように咲く朝顔が鮮やかです。
やわらかいグリーンの兵児帯が柔らかい印象を与える3点セットの浴衣になります。
撫子の意味
可憐な日本女性を「大和撫子」と言うように、清楚で慎ましやかなイメージの花です。
古くは万葉集、枕草子にも登場し、貴族にも愛された花です。
また、「大胆」「勇敢」といった力強い花言葉もあり、静と動を巧みに使う日本女子サッカー、なでしこジャパンでも使用されています。
撫子(なでしこ)柄浴衣のおすすめ
白地に淡いサーモンピンクとオレンジが優しい印象の浴衣です。
透き通るような撫子のグラデーションが儚いイメージを与え、麻の葉文様の黄色い帯できりりと引き締めています。
浴衣の始まりまとめ
ゆかたは庶民の手に届くようになってからあっという間に広がりました。
生活が洋式化すると浴衣も目立たなくなっていきますが、浴衣のよさを知る現代人も浴衣をあえて着る習慣になっています。
この習慣を無くさないようにあえて浴衣を着るのも日本人の遺伝子かもしれませんね。