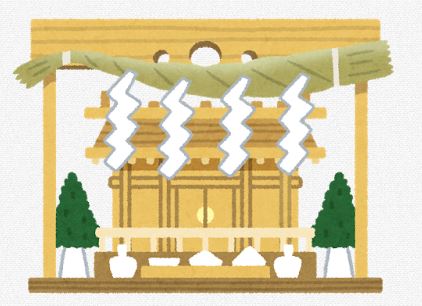
長年、家族を見守ってくれた神棚。いざ新しくしようと思っても、「古い神棚って、どうやって処分すればいいの?」「ゴミとして出したら、バチが当たりそうで怖い…」と悩んでしまいますよね。
大切なお守りを神社でお焚き上げしてもらうように、神棚も同じで良いのでしょうか?
間違った方法で処分して、何か良くないことが起きたらどうしよう…と不安に思うお気持ち、とてもよく分かります。
ご安心ください。この記事を読めば、あなたの状況に合った、丁寧で安心できる神棚の処分方法が分かります。感謝の気持ちを込めて、きちんと神様にお還りいただくための手順を、一つひとつ丁寧に解説していきますね。
そもそも「お焚き上げ」とは?

まず基本として、「お焚き上げ」について知っておきましょう。
お焚き上げとは、魂が宿っていると考えられ、粗末に扱うことができないお品を、神社やお寺で神主様や僧侶の方が祈りを込めて供養し、火で燃やすことで天にお還しする儀式のことです。
まさに、家と家族を守ってくれた神棚は、この「粗末に扱えないお品」の代表格です。
他にも、お仏壇、お位牌、お守り、だるま、故人の写真や手紙、子供が大切にしていたぬいぐるみなどもお焚き上げの対象となります。
古い神棚の処分方法は4つ!あなたに合うのはどの方法?
- 神社・お寺に持ち込んでお焚き上げしてもらう(一番丁寧で安心)
- 専門業者に郵送してお焚き上げしてもらう(忙しい・近くに神社がない方向け)
- 供養もしてくれる不用品回収業者に依頼する(他の家具とまとめて処分したい方向け)
- 自分で供養してお清めしてから処分する(最終手段)
それでは、各方法の具体的な手順や費用を詳しく見ていきましょう。
方法①:神社・お寺に持ち込んでお焚き上げ
今までお世話になった神社(氏神神社)や、近所の神社・お寺に直接持ち込む、最も一般的な方法です。
【手順】
- 神棚を購入した神社や、お札をいただいた神社、または近所の神社・お寺に電話で問い合わせます。
- 「古い神棚のお焚き上げをお願いしたいのですが…」と伝え、①受け付けてもらえるか、②持ち込みの日時、③費用(お焚き上げ料・初穂料)、④神具(陶器など)も一緒に持ち込んで良いかを確認しましょう。
- 指定された日時に、感謝の気持ちを込めて神棚を持参します。
【費用の目安】
お気持ちで良い場合や、無料の場合もありますが、3,000円~10,000円程度が一般的です。のし袋に「お焚き上げ料」や「御初穂料」と書いてお渡しすると丁寧です。
神社によっては、神棚の大きさ(一社型、三社型など)で料金が決まっている場合もあります。
(例:一社型(御神札を重ねて祀る形)で千円、三社型(御神札を並べて祀る形)で三千円など)
【注意点】
- 突然持ち込むのはNG! 「どんど焼き」のような決まった日にしか受け付けていない場合や、そもそも他所のお札や神棚は受け付けていない場合もあります。必ず事前に電話で確認しましょう。
- 神具は対象外なことが多い: 陶器・ガラス・金属製の神具(お皿や瓶子など)は燃えないため、お焚き上げの対象外です。これらは自分で清めてから、自治体のルールに従って不燃ごみとして処分するのが一般的です。
方法②:専門業者に「郵送」でお焚き上げ
「近くに頼める神社がない」「忙しくて持ち込む時間がない」という方に便利なのが、郵送専門のお焚き上げサービスです。
【手順】
- インターネットで「神棚 お焚き上げ 郵送」などのキーワードで業者を探します。
- サイトから申し込み、料金を支払います。
- 業者から送られてくる梱包キット(ダンボールや申込書など)を使って神棚を梱包します。
- 郵便局や宅配業者から発送すれば完了です。
【費用の目安】
神棚のサイズによりますが、5,000円~15,000円程度(送料込み)が相場です。
【注意点】
信頼できる業者を選ぶことが大切です。きちんと提携している神社で供養を行っているか、サイトで実績などを確認すると安心です。
方法③:不用品回収業者に依頼する
大掃除などで他にも処分したい家具がある場合に便利な選択肢です。ただし、業者選びには注意が必要です。
【手順】
- 不用品回収業者に連絡し、神棚も回収してほしい旨を伝えます。
- この時、必ず「合同供養」など、きちんと供養してから処分してくれるかを確認しましょう。
- 見積もりに納得したら、回収を依頼します。
【費用の目安】
他の不用品とまとめて数千円~、という料金体系が多いため、神棚単体だと割高になる可能性があります。供養のオプション料金がかかる場合もあります。
【注意点】
業者によっては、ただの「木材」として他の不用品と一緒に処分するだけのところもあります。大切な神棚ですので、必ず「供養」の有無を確認し、信頼できる業者を選んでください。
方法④:自分で供養して処分する
どうしても上記の方法が取れない場合の最終手段です。ご自身で感謝を伝え、お清めをしてから処分します。
【手順】
- 神棚からお札や神具を取り出します。
- 神棚の前に立ち、これまでの感謝を込めて二礼二拍手一礼をします。
- 塩を振りかけてお清めをします。
- きれいな白い布や紙に包みます。
- 他のゴミとは別の袋に入れ、自治体のルール(可燃ごみなど)に従って処分します。
【費用の目安】
ほぼ無料です。
【注意点】
最も手軽ですが、「本当にこれで良かったのかな…」と後々気になってしまう可能性も。少しでも心に引っかかりを感じる方は、神社やお焚き上げ業者に依頼するのが安心です。
神棚の処分に関するQ&A
-
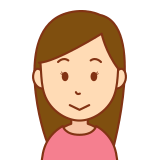
Q. 処分するタイミングはいつが良い?
-
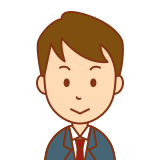
A. 特に決まりはありませんが、年末の大掃除の時期や、神社で「どんど焼き」が行われる1月中旬、あるいは新しい神棚に買い替えるタイミングで処分する方が多いです。
-
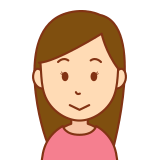
Q. 新しい神棚の魂入れはどうするの?
-
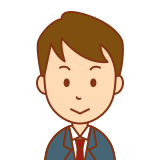
A. 古い神棚をお焚き上げした後は、新しい神棚に新しいお札をお迎えしますよね。新しい神棚にも、神様の魂をお迎えするための「魂入れ」をしていただくのが理想です。こちらも神社やお寺に依頼することになりますので、古い神棚の処分の相談をする際に、一緒に「新しい神棚の魂入れもお願いできますか?」と確認しておくとスムーズです。もちろん、別途おこころざし(初穂料)が必要となります。
-
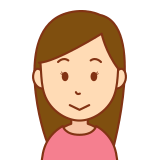
Q. 古いお札はどうすればいい?
-
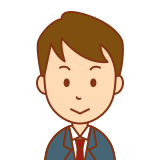
A. 古いお札は、神棚を処分する際に一緒に納めるか、お札だけを神社にある「古札納所(こさつおさめしょ)」にお返しするのが一般的です。一年間お守りいただいた感謝を伝えてお納めしましょう。
まとめ:感謝を伝えて、気持ちよく神棚を処分しよう
この記事では、古い神棚の処分方法について解説しました。
- 神棚の処分は、神社やお寺での「お焚き上げ」が基本。
- 忙しい方や近くに神社がない方は、郵送サービスも便利。
- 処分を依頼する前には、必ず事前に電話で日時や費用を確認しましょう。
- 新しい神棚を迎えるなら、「魂入れ」も併せて相談するとスムーズです。
一番大切なのは、これまで家族を見守ってくださったことへの感謝の気持ちです。
どの方法を選ぶにしても、ご自身が「これで安心」と思える方法を選んでくださいね。
もし少しでもご不明な点があれば、ご自分で判断せず、まずは近所の神社やお寺に相談してみることをお勧めします。きっと親身に教えてくれますよ。